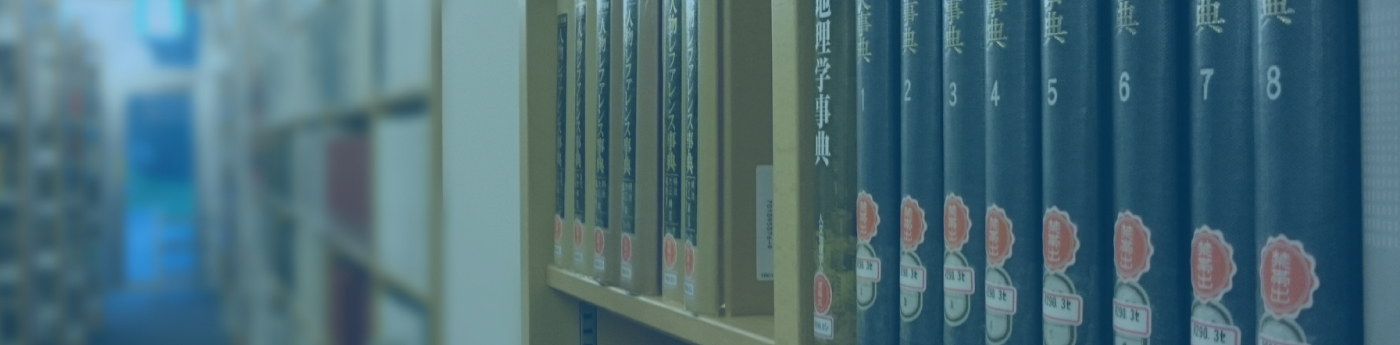濱谷 真理子(はまや・まりこ)
教育分野(領域)
地理学・社会学・文化人類学・社会文化学分野(文化人類学)
研究・教育のキーワード
宗教人類学、巡礼、ヒンドゥー教、贈与論、ジェンダー、社会福祉、移民、慈善活動、四国、インド、英国
研究者としての私
私が人類学にであったのは23歳のとき。何が何だかよくわからないまま授業で生産直売所のフィールドワークに挑戦しました。参与観察やインタビューを通じて人びとの生活世界に巻き込まれていくのが楽しくておもしろくて、結局その後直売所のオーナーの家に下宿させてもらって卒業までアルバイト兼調査を続けました。それをきっかけに、これまで四国、インド、英国をフィールドとして、「宗教が地域の人びとにどのように生きられているのか」をテーマに研究を行ってきました。四国では、八十八ヶ所を托鉢しながらまわり続ける「乞食遍路」について、インドではヒンドゥー教女性出家修行者について、自分も遍路や修行者になって調査を行いました。2〜3年前から、英国のインド系女性移民の慈善活動、特にボランティアについて、自分もボランティアをしながら調査をしています。
教育者としての私
文化人類学は、研究者の人生を変える学問だと思っています。
前述したように、私はフィールドワークのなかで、お遍路さん、修行者、ボランティアなど、調査協力者の世界の一部になろうと努めてきました。そうした<変身>は、日々の生活で時に凝り固まった思考や身体をときほぐし、ちがった形の<世界>や<生き方>へといざなってくれるものとなりました。そして、経験したことをすべてフィールドノートとして書きとめ、それをエスノグラフィー(民族誌)として記述する営みは、ちがった形の生きる意味を私に与えてくれました。人生には楽しいことだけでなく、苦しいことや悲しいこともありますが、すべてエスノグラフィーの糧になると思えることで、直面する問題を乗り越えることができるからです。
毎日がフィールドワークであり、未来のエスノグラフィーの一部を私たちは生きている。文化人類学は一つの学問でありながら、同時にそうした生きるための知恵や技を教えてくれる<生の技法>でもあります。それがどういうものかは、経験してみないとわかりません。もっと知りたい、自分も変身したい、人生を変えたいと思った方は、ぜひ一緒に人類学しましょう!
私が書いたもの
学術書なので議論の部分は少し難しいかもしれませんが、エスノグラフィー部分は読みやすいと思います。北インドの「家住行者」と呼ばれる半僧半俗の女性たちの日常生活について描いたものです。
・濱谷真理子、『出家と世俗のあいだを生きる──インド、女性「家住行者」の民族誌』、風響社、2022年。
ヒンドゥー教の出家修行者に興味のある方は、事典項目を読んでみてください。どんな人びとでどういう世界を生きているのか、輪郭がわかると思います。
・濱谷真理子、「現世放棄者の世界」、『インド文化事典』、丸善出版、pp.70-71、2018年。
そのほか、修行者の衣装について書いたものや、2011年の東日本大震災とちょうど時期が重なった南インドのヨーガ道場ツアーについての原稿があります。読みやすいので、よかったらこちらもぜひ読んでみてください。
・濱谷真理子、「衣服がつくりだすつながり─インド・ハリドワールの女性出家者」『月刊みんぱく』、第45巻11号、pp.4-5、2021年。
・濱谷真理子、「『聖地の旅』と震災──日常世界とフィールドのあいだから」『アジア・アフリカ地域研究』、第11巻1号、pp.68-72、2011年。