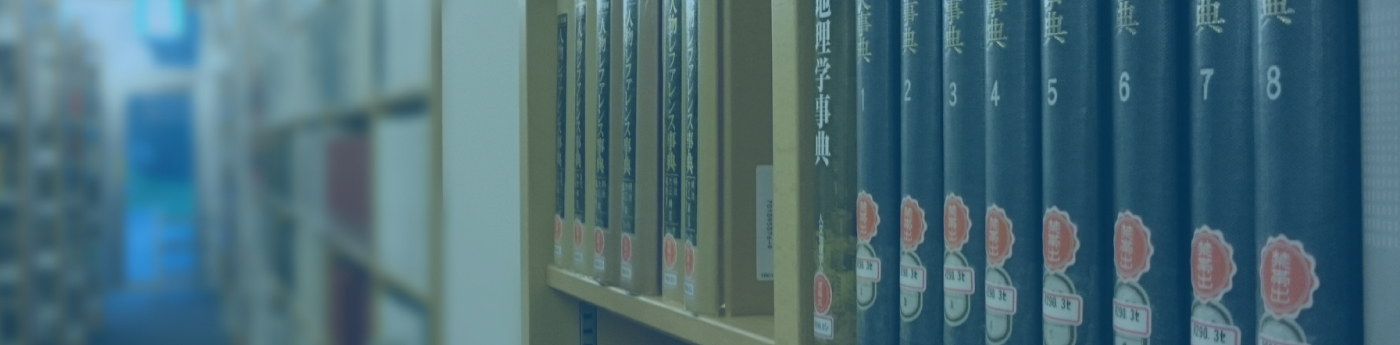講演会「疑問詞疑問文と二つの条件終止形 —岡山玉野の地域の方言を中心に」のお知らせ(12/11開催)
講演題目:疑問詞疑問文と二つの条件終止形 —岡山玉野の地域の方言を中心に
講師:田窪行則(国立国語研究所 客員教授)
日時:2024年12月11日(火)午後2時から4時
場所:文法経1号館2階文学部会議室
使用言語:参加無料・申込不要
講演要旨:
岡⼭⽅⾔では疑問詞と条件形の⽂終⽌⽤法が共起制限を持つことが知られている。この現象に最初に注⽬した⾍明(1958、82)は、これを古代語の係結び構⽂と関係させて論じている。最近では、三宅(2004)はこれを係結びとは呼ばず、条件形が屈折辞として、Wh要素と関係を持つ現象であるとしており、ある種の焦点⼀致構造(focus agreement)と捉えているように読み取れるが現象のとらえ⽅は⾍明を継承している。
⾍明も三宅も「なら」「りゃー((r)ja:)」「たら」の3つの条件形すべてにこの⽤法があり、同じような機能を持つと考えている。しかし、⾍明のあげている「たら」の例は条件形とは認められず、条件終⽌の⽤法ではないと考えられる。
本稿では「なら」と「りゃー」のみが条件終⽌形を持つと考えて、疑問詞と条件形終⽌⽤法との共起制限の性質を整理して記述し、次のように主張する。
(1) この構造では疑問詞が条件終⽌形を要求するのではなく、条件終⽌形が疑問詞疑問⽂を
要求する構造と捉える。
(2)「なら」は未然形の「ならば」ではなく、已然形に「ば」が付いたものであり、理由を
あらわす既定条件が⽂末形式に⽂法化したものである。
(3) 条件終⽌の「なら」は、それが名詞相当語句につくことから、まだコピュラとしての性
質を残しており、「のだ」にあたる機能を果たす。
(4) 条件終⽌の「りゃー」は「よー」「だろう」と似た機能を果たす。これは、終⽌形に
「やら(む)」がついた形と考えれば、その機能を記述できる。
(5)(1−3)によると、これまで同じように条件終⽌と考えられていた2つの形式は別の構
造を持つと考えられる。
講師略歴:
前日本言語学会会長
前国立国語研究所所長
京都大学名誉教授
岡山県玉野市出身
https://researchmap.jp/yukitakubo
【コメンテーター】角道正佳 大阪大学名誉教授、岡山県玉野市出身
主 催:岡山大学 文学部 言語学・現代日本語学領域
連絡先:kuri[@]okayama-u.ac.jp 栗林裕